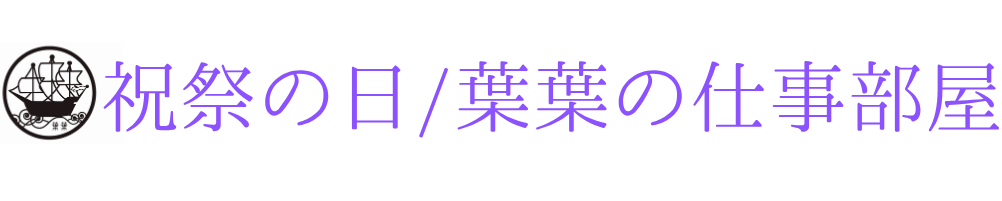『サラ・スペックス、知られざる少女。』その2
第一章 バタヴィア城ーa 1626年4月
この物語は、1626年4月のバタヴィア城から始まる。

船が北からバタヴィアの海岸に近づく時、まず見えて来るのは、漆喰で固めたいかめしい城壁である。
これがいわゆるバタヴィア城であり、総督や彼の補佐役である東インド評議員ははじめの中ここに起居した。他のオランダ植民地の要塞と同様、土地の風物とは不似合いな西洋風の要塞である。全体のプランは正方形で、四方に三角形のやぐらが張り出し、敵に備える形となっていた。やぐらにはダイヤモンド、ルビー、サファイア、真珠というやさしい名前がつけられていた。
城壁の一辺の外側が280メ—トル、内側が150メートル位であったと思われる。
城の周囲には掘割がめぐらされ、南側にある橋だけが城の中と外とを繋いでいた。掘割の水にはボゴ—ルの東方の山から流れ出てバタヴィアを貫流するチリウン河の水を引いている。
天然の河をいくつもの運河に分けて市街を縦横にめぐらすのはオランダ人のお家芸である。アムステルダムの運河は中央広場を中心とする同心円状のものと放射状のものとの複雑な組み合わせから成っていたが、バタヴィアのはデルフトなどと同じく碁盤の目のようで、見た目には整然と、町のプランを決定している。そしてオランダ人はこの外郭にも城壁を造り、その上に一定の間隔を置いてやぐらを造った。
この城壁にかこまれた南北約1,400メ—トル、東西約1,000メ—トル位の地域がバタヴィアの町であった。城壁の南側に唯一つの城門があり、前の掘割にはゴッホの絵を思わせるようなはね橋がかかっていた。
『オランダ東インド会社』永積昭著 P180抜萃(講談社学術文庫,2000年刊)

牧師がその少女を初めて見たのは、バタヴィア城でだった。
1626年4月のある日、ジョルジウス・カンディディウス Gorgius Candidius は目の前にそびえる城塞を見上げていた。
その横顔には疲労と倦怠があった。宣教師としてアジアに渡ったのは三年前だが、溢れる宣教熱は海水やら泥水やらに何度も冷やされた。
牧師は重厚な城砦を眺め、「赤道直下には耐え難い・・」と苦い顔をした。
近くの港には積荷が次々と降ろされ、荷揚げ人や商人達が忙しく行き交っていた。香辛料の大きな麻袋を担ぐ人々がいた。痩せた荷揚げ人は麻袋から豆をこぼしながら担いでいた。白い顔、黒い顔、茶色い顔、西洋人に東洋人、どの国の者かわからない顔。服装も多種多様である。この炎天下、黒いツバ広の帽子に天鵞絨をまとうオランダ人もいれば、腰に布を巻きつけただけの男もいる。革靴、草履、素足。見事なほどの世界の縮図だ。
城門へ続く橋の手前で、牧師はある一角に目を留め、眉をひそめた。鉄の足枷を引きずる奴隷の一群であった。ベンガル辺りから運ばれてきたのか、ジャワ人とも違う風貌の人々である。虚ろな目をしている。赤ん坊を抱く女奴隷。母の足元から離れない子供の奴隷。早晩引き離されるのだろう。頑丈な男、美しい女のみ選り分けられ、― 彼らとて奴隷扱いは同じだが― あとは十把一絡げの雑魚となる。幼児等は量り売りされる。
これがわが社、VOC(オランダ東インド会社)の現実なのだ。
「ジョルジウス、早く橋を渡れ」
先を歩くヘルマン牧師が振り返り、カンディディウスの視線の先に気付いた。
「あんな光景にも慣れねばな」
「慣れる?」
ジョルジウスの鋭い目を、ヘルマンは冷笑ではね返した。
「君は性急すぎるんだ。だから、ル・フェーブルに讒言され・・」
「貴殿までがそのような」
城門で二人は身分証の提示を求められた。
「・・ヘルマン牧師先生。こちらはカンディディウス牧師先生。失礼致しました。どうぞ中へ」
カンディディウスは、昨年まで、モルッカ諸島、テルナーテの布教に従事していたが、長官ジャックス・ル・フェーブルJacques le Febreと対立し、バタヴィアに送還されたのであった。ヘルマンが「ル・フェーブルの讒言」と言ったのはそのことである。
城内に入ると風景は一変した。煉瓦造りの城、小ぎれいな装いの人々。まるでオランダである。
「ヘルマンよ」
ジョルジウスはむっとして言った。
「私は当然の忠告をしただけ。先住民を虐待するなと。土地の女を弄ばぬようにと。ところが長官はバタヴィア総督に、ありもしないことを書き送り・・」
そこに楽隊の音が鳴り響いてきた。近衛兵の行進である。見るからに凛々しい上級兵らが行進し、それに遅れじと質素ななりの下級兵が続く。たちまち土埃が湧き起こった。
「え?何だって? え? え?」
行進の音にかき消されぬ様、ジョルジウスはいつしか大声になっていた。
「わが社は無限の可能性を秘めている! しかし、その力を神の為に使ってはいない! 彼らが目指すのは「金もうけ」だ! テルナーテ、ジャワ、アンボイナ、バンダ・・あらゆる地域を占領し、香辛料を根こそぎ手に入れ、抵抗する先住民を殺害する。いいかい、オランダでは英雄と言われる総督クーンこそ残虐な人間だ! クーンもル・フェーブルも日曜礼拝に来れば血で染まったその両手を聖水で洗い清め、何食わぬ顔で主の御前に跪 くのだ。それを、見て見ぬふりする牧師だけが喜ばれる。会社に雇われた牧師など所詮「社畜」だ。この三年でようく分かった。カトリックの宣教師達が東洋で、命がけの宣教をしているのを汝は知っておろう? 彼等をローマ教皇の飼い犬と嘲るが、社畜よりよっぽどマシではないか!」
「おいっ、聞かれる!」
「聞かれて結構!」
ジョルジウスの剣幕にヘルマンは辟易した。〝まったくなんだってこんなにクソ暑いんだ〟〝灼熱の太陽は俺らの脳天を焼け焦がし、聖人さえ節操を無くす〟。汗を拭くヘルマンにジョルジウスはなおも言い放った。
「ヘルマン牧師よ。日本の魔王ヒデヨシを知っておろう? ヒデヨシに処刑された二十六聖人を知っておろう? 彼等は拷問に耐え、主の御名を讃えながら十字架の上で亡くなったのだ。われらは金儲けの片棒をかつぐために主に召し出されたのか? 東洋の国々、未開の人々や偶像崇拝の人々、邪教を信ずる人々に主の御言葉を届ける事が宣教師の使命ではないのか。せめて私は新教国の水晶でありたいのだ」
「わかった、わかった。水晶な。わかったから、もそっと静まれ」
「こんな苛立ちは貴殿にしか言えん」
「貴婦人が驚くぞ。おお、これはこれは・・」
ヘルマンは立ち止まって三人の婦人に会釈した。カンディディウスに気付いてさっきからこちらを見ているらしかった。別の婦人達も遠くから見ている。そちらへもヘルマンは愛想を振りまき、婦人らは優雅に返礼した。
「ジョルジュ、人気者だな」
「・・・」
「昨日のジョルジュの説教は良かった。未開地での命がけの宣教と、最後に信仰を受け入れたあの親子の話・・。すすり泣くご婦人さえいたぞ」
「・・・」
「バタヴィア滞在中にどうだい? 身を固めては」
「上流階級の娘とか? 笑わせるな」
「又そんな事を。深窓の令嬢で、心の美しい、地の果てまで付いていく・・そんな聖女がいるやも知れん」
「砂浜から一粒の真珠を探し出すようなものだ」
ヘルマンは派手に笑った。
「まあ、せいぜいサタンの罠にかからぬ様にな。ラッセル牧師のように」
ラッセル牧師―― 。バタヴィアで酒と女に溺れ、バタヴィアから叩き出された元牧師のことである。女奴隷さえ孕ませた。
「怒るぞ!」
「怒るな、怒るな。ほら、もう執務室だ」
バタヴィア城の総督公邸には、モルッカから共に渡った船の船長や上級商務員等も招かれていた。彼等はモルッカの状況、商取引の詳細を総督ピーテル・ド・カルペンティール Pieter de Carpentier に報告し、総督はねぎらいの言葉を一人一人にかけていた。かの総督クーンは三年前に総督職を剥奪され、本国に返された。「アンボイナ事件」をめぐってイギリスからの非難が止まなかったのだ。
「カンディディウス牧師様ですな」
総督カルペンティールは手を差し出した。
「神の御使いへのご挨拶が最後となりました。どうかお許しを」
「いえ」
一呼吸置いてから、「して」と総督は牧師ににじりよった。
「長官からの訴えがありましてな」
笑顔ながら鋭い目で牧師を品定めした後、得心した如く目尻にシワを寄せて言った。
「長官のことはお気になさるな。品性下劣な人間で、信仰は二の次だ。牧師様も辛いお立場だったことでしょう。しかし、わがバタヴィアは牧師様を歓迎致します。ここで、我々の魂を耕して頂きたい」
ヘルマンが割って入り、「総督、オランダ送還だけは、是非とも・・」と頭を下げた。
「ほら、あなたからも総督に」
ヘルマンに促され、カンディディウスもまた「宜しくお願い致します」と通り一遍の挨拶をした。ヘルマンは如才なく高官等と挨拶を交わし出した。カンディディウスはヘルマンを横目で見た。
―どうともなれだ―。
そして、見るとはなしに、部屋に飾られた大振りの絵画・・「ポルトガル船との闘い」、「バンダム軍との死闘」、「バンダナイラ島制圧」を眺めた。
―こうやって、何千、何万人もの血が流された・・。
型通りの儀式が終わると、来訪者たちは広間に通された。シャンデリアの輝く豪華な広間である。テーブルに置かれた大皿には料理が盛られ、葡萄酒や地酒の類も並んでいた。そして、総督の家族、上級商務員等とその家族がすでに談笑していた。新参者とバタヴィア在住の高官達との一種の顔合わせの場なのである。婦人等の色とりどりのドレス姿が広間を華やかな社交場にしていた。部屋の隅々で使用人達が大うちわで風を起こしている。その風が婦人等のドレスの裾を揺らしていた。
美しい女性が微笑みながら近づいて来た。
「牧師様」
カンディディウスは会釈した。
「昨日の礼拝に参りました。牧師様のお説教に感銘を受けました」
「恐縮です」
「ずっとこの街にいらっしゃれますの?」
軍医長ミラーの娘だという。モルッカではめったに出会えない西洋人だ。金髪を縦ロールにして、腰を絞ったドレスを着ていた。良い香りがした。これがヘルマン言う所の聖女なのだろうか。カンディディウスは、娘の問い掛けに答えつつ ―違うな。―と思った。シラヤ族の女の方が私には似合いだ。素朴で清らかだ。会社はシラヤ族との結婚など認めそうにないが。
何気なく広間を見回した時、カンディディウスは一人の少女に目に留めた。混血少女である。まあるい額。まあるい頬。そこに大きな目がぱっちりと開いている。人形のようだった。脇に立つ男は父親であろう。男はカンディディウスに気が付くと、遠くから頭を下げた。それを潮に牧師は縦ロールの娘に一礼して男のもとに赴いた。
「ジョルジウス・カンディディウスと申します。改革派教会の牧師でございます」
「お名前はかねがね・・」
男は深々と礼をした。物腰は柔らかく、威厳があった。
「ヤックス・スペックス Jacques Specx と申します。事務総長をしております」
「しばしこの地に滞在致します」
ジョルジウスが礼をした時に少女と視線が合った。少女は牧師を見上げ、ドレスをつまんで可愛く挨拶した。本当に人形のようだ、そう思った。
「お嬢様ですか?」
「ええ、娘のサラSara。ジパング生まれでございます」
「ほお、ジパング・・」
「私は平戸にかれこれ十三年おりました」
「フィラド・・・」
「ええ、長崎の・・」
「長崎!」
カンディディウスの脳裏にはたちまち『Het Martelaarschap van de 26 heiligen van Japan 』―日本二十六聖人の殉教― の磔刑図と、ヒデヨシの挿絵が浮かんだ。
「スペックス様の頃は魔王ヒデヨシは御在位でしたか?」
スペックスは刹那、ぎらりと相手を見た。ライデン大神学部を主席で卒業した逸材。長身の知的な切れ者。なるほど、社の方針とことごとくぶつかるので評議会の俎上によく上がる牧師がこの男・・・。
「いえ、ヒデヨシは既に亡く、大御所イエヤスの御世でございました。強大なヒデヨシ配下を打ち破り、ジパングの統一を成し遂げた賢王でございます。度々拝謁を許されました」
「一度行ってみたい国です」
スペックスは笑った。
「牧師様、ご冗談を。それはご無理です」
「・・・」
「日本国はイエズス会に荒らされましてな。国王はキリスト教を蛇蝎の如く嫌悪し、宣教師を殺し、信徒を殺し、キリスト教関連品の一切の輸入を禁止致しました」
「輸入品までも・・」
「牧師様は一歩たりとも日本の地にお立ちになることは・・」
牧師は踏み込んで言った。
「そのような〝試みの地〟に潜入しようとするカトリックの神父は敵ながらあっぱれ。われらプロテスタントの牧師も見習いたいものです」
「めっそうもない」。スペックスは肝を冷やした。
「危険思想ですぞ、牧師様! オランダ貿易を破壊するおつもりか。ゆめゆめ日本潜入などお考えになりませんように」
スペックスは脇の下に嫌な汗をかいた。平戸商館で神父を鞭打った、その感触が一瞬掌に蘇った。
「スペイン、ポルトガルはそれで手痛い打撃を受けました。南蛮船が入港禁止になる日も近い。日本国王がどれほど禁止しても宣教師が密入国をやめませんので」
スペックスはハンカチで汗をぬぐった。
「世にも珍しき〝平山常陳事件〟なるものがございました。いやはや。私が商館長時代でございます。二人の宣教師がゴシュインセン―― 国のお墨付きの船という意味ですが――の船底から見付かり、商館の地下牢に収攬した事がございます。自分達は商人だと言い張るのを私共は裁判で宣教師の証拠を付きつけ、その結果、宣教師二人と船員ら十数名が処刑されました。それに連動し、別件で捕獲されていた司祭と信徒50余名も火あぶりです」
牧師の顔が歪んだ。
「おぉ、牧師様、誤解なさいませんように。どうか・・。もちろん私にとりましても嫌な事件でございました。元々同じキリスト教徒。いやいや、私が申し上げたいことは、イエズス会士のように、がむしゃらに宣教を急がれるなということでございまして・・」
スペックスは「おい、窓を開けなさい!」と下男らを怒鳴った。
「運河からの風が悪しき病を運ぶなどと言う輩がいるのですよ。この灼熱地獄の中で窓を閉め切るとは・・」
そう笑って、流れ落ちる汗を拭いた。
「なにごとも〝時〟が肝心。その時が来ますれば、宣教に乗り出せば宜しい」
「事務総長殿・・それはごもっとも」
バタヴィアの熱気は頭のどこかを麻痺させる。この時、何故かジョルジウスは苛立ちを抑えきれなかった。
「しからば、牧者を失った羊の群れはどうなりましょう。ジパングにはキリシタンが40万とも50万とも言われておりますが」
事務総長は言葉に詰まった。
―それ、それ! その信仰心が商売を破壊するのだ!
スペックスはその言葉を飲み込んだ。
張り詰めた空気の中に猫の様な鳴き声がした。・・・おとうさま。・・
少女の声だった。
「おとうさま・・お腹がすいた」
スペックスは傍らの娘に気付くと、ほっとしたように「おぉ、すまんな」と少女の頭をなでた。
牧師も柔和な顔に戻った。そして「言葉が過ぎました」と詫びた。
「事務総長殿、どうかご心配なさいませんように。日本は私にはあまりにも遠い国でございます」
「はは。そうですとも。無茶はいけません。無茶は」
スペックスは再び汗を拭った。
牧師はしゃがんで少女と同じ目の高さになった。
「何が食べたいのですか? お菓子ですか? 果汁ですか?」
「冷たいマンゴー」
バタヴィア城には氷菓子さえあるらしい。牧師は笑って両手を広げた。
「さあ、いらっしゃい。探しましょう」
少女は牧師の腕の中にすんなり飛び込んだ。
オランダの少女に比べて小柄なサラは六、七歳にしか見えなかったが、この時、サラは九つであった。
「ああ、牧師様のお洋服が汚れます。これ、サラ。ああこれ、サラよ、サラよ」
「構いませんから」
牧師は笑顔で娘を抱いたまま、氷菓子を探してテーブルを巡った。長身の牧師が愛くるしい少女を抱く姿に、テーブルを巡る度にそこに小さな歓声が沸いた。
少女の淡い栗色の髪の毛はふんわりとカンディディウスの頬をくすぐった。肌は白くなめらかで、薔薇色の唇をしている。どこがどうと言えない混血の子の愛らしさがあった。
総督クーンは純血種を意固地なまでに奨励するが、違う人種同士の結合はかくも美しき幼な子の誕生を見る。神が嘉されている何よりの証拠ではないか。ジョルジウスは少女のつぶらな瞳をそっと覗き込み、神の御業を思った。
カンディディウスのバタヴィア滞在中、この少女は一度も改革派教会に来ることはなかった。ヘルマンは、少女はポルトガル教会(カトリック)に通っているのだと言った。ポルトガル教会はカリブ・サール大運河を隔てた西の外れにあった。
まれにバタヴィア城で見かけることもあった。いつも着物を着た日本の婦人と大勢の付き人がいた。伴の者達に守られるように、小さな姫は、大概はしとやかで、時には子供らしく快活に歩いたり、友達と遊んだりしていた。城門を出る時には、男達の担ぐ輿に乗っていた。
牧師を見つけると少女は手を振った。日本人の家でひな人形を見たことがあったが、少女を見るたびに彼はその人形を思い出した。
さて、牧師ジョルジウス・カンディディウスはしばしバタヴィアの地から消える。
次の任地は、当時 Formosa ―ポルトガル語で美しい島―と呼ばれた台湾だった。VOCは1624年、中国人、日本人、海賊ら外敵のひしめく中、台南安平に熱蘭遮城を築いた。VOCは台湾がアジア経営の拠点となることを見越して、気骨あるカンディディウス牧師を台湾に据えた。それ以後、彼は台湾布教という困難な仕事に心血を注ぐことになるのである。
そして、父ヤックス・スペックスも同時期にバタヴィアから消える。こちらは本国オランダからの招集だった。十七人重役会はスペックスにある嫌疑をかけた。その弁明のため、オランダ滞在は思いのほか長期に亘り、娘サラはたった一人でバタヴィア城に残されることとなった。