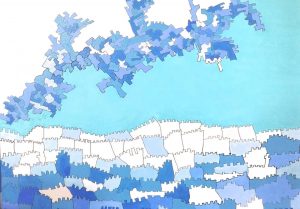ホーソンの『緋文字』を読む。
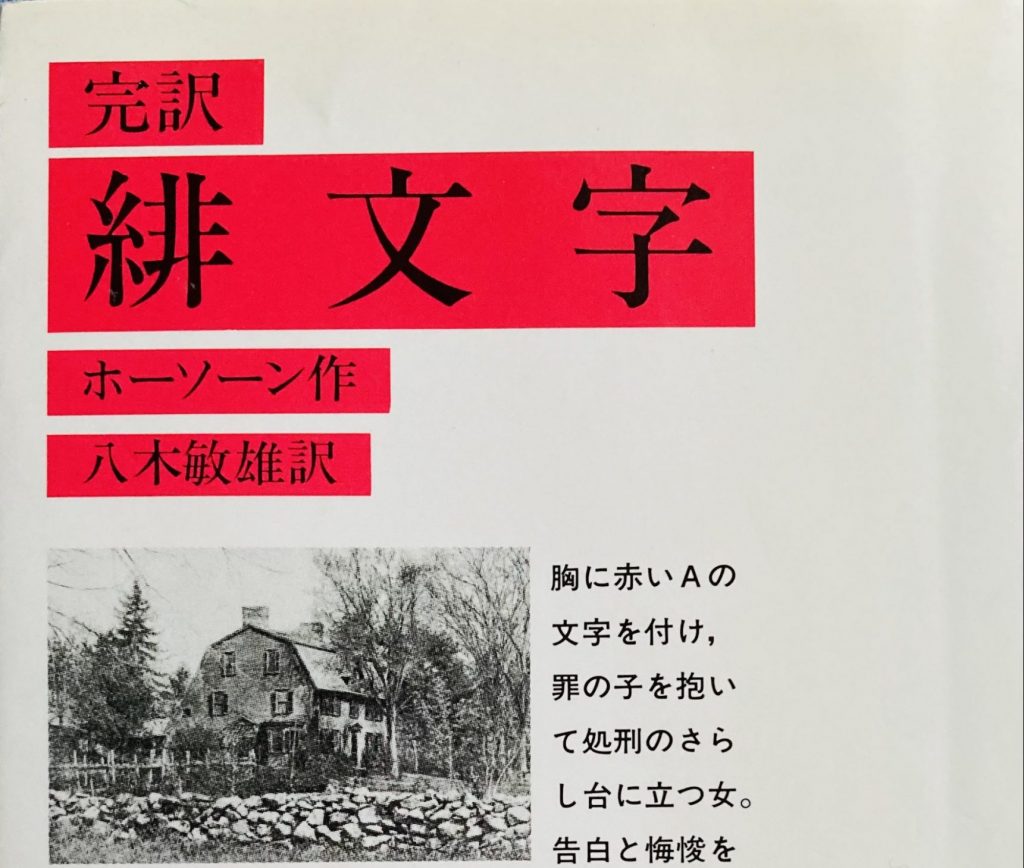
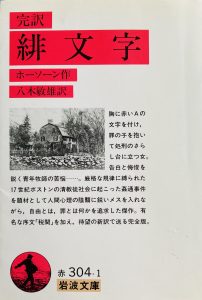
古典と言われる書は「いつか読まねば」と思いつつもその機会を逃してしまいがちだ。
その中の一つ、ホーソンの『緋文字(ひもんじ)』をやっと読む日が訪れた!
私の所属する「吉祥寺キリシタン研究会」はコロナ禍で集会が休止。それに代え「研究会通信」を発行することになったが、その中で二人の方が『緋文字』を取り上げた(→参考レポート➀「緋文字」を読んで。古田和子氏/ ②ホーソン「緋文字」を読む。吉川豊子氏。ちなみに古田氏はカトリック教会所属。吉川氏はプロテスタント教会所属)。
それらが興味深かったので、私もその論争(?)に参入してみたくなったのである。
さて、この小説、外国文学にありがちだが、「序章」がやたら長い!
平素ならそこで挫折するところだが、粘り強く読み進めると、さすが、心理描写の細やかさ、サスペンス風の流れ、等々に引き付けられ、最後まで読み切ることができた!水先案内人のお二人には感謝である。
この読み応えのある長編小説を多くの方に知ってほしいとの思いから、ブログに私のレポートを載せることにした。

画ヒューズ・メール
あらすじ
舞台は1640年代、開拓時代のアメリカはボストン。厳格なピューリタン社会にスキャンダルが起きる。夫が消息を絶ち寡婦のように暮らしていた美貌のヘスター・プリンが子を身籠り出産する。そして相手が誰かを隠し続ける。姦淫の罪により、彼女は処刑台に立ち、衆人の前でさらし者となる刑を受ける。そして生涯、緋色の「A」(=姦淫Adaultery)の文字を服の胸に付けて生きることを命じられる。
密通の相手は人望ある若き牧師デムスデールであるが、彼は自分の立場と信徒たちへ与える影響の大きさを考え、黙したまま悩みを深めていく。
さて、本編の冒頭の、ヘスターが処刑台に立つのを見ていた大衆の中に消息不明だった夫チリングワースがいた。医者としてこの町に到着した日に妻の不貞を知ったのだった。そして持前の嗅覚から妻の相手が牧師デムスデールであることに彼だけが気付く。二人への復讐心に燃えたこの夫は正体を隠し牧師に近づき、精神的な治療と称して牧師の内的苦悩を掻き立てて悪魔的に追い詰めて行く。
同じ罪を犯した二人(ヘスターと牧師)の全く違う試練の日々が七年間続く。一方は〝あばずれ〟と罵られつつ徐々に周囲からの信頼を取り戻し・・・もう一方は〝聖なる人〟と賛美されることで、欺瞞に満ちた自分への嫌悪感と罪の重さに心身を病む。
終盤、森の中でヘスターと娘パールは牧師と偶然出会う。憔悴しきった牧師を見て、ヘスターは「三人で新しい土地へ行き、新しい生活を始めましょう」と提案する。牧師もこの提案に一筋の光明を覚える。
さて、牧師が選択した道は・・・。
通信第一号で古田さんが〝ミルフィールのように重層的〟、更に二号で吉川さんが〝フーガのように〟と語っておられた『緋文字』。お二人の言葉にひかれ『緋文字』を読んでみました。私のは古田さんと同じ岩波文庫本(八木敏雄訳)です。
読了後の今、思いますのは、しっかりした構成の中に細部(人物像の複雑さ、心理描写の細やかさ)が丹念に描かれていたなということです。ですから、どの視点から切り取っても考察に耐えうる小説となっていると思います。
さて、主人公へスターですが、私も吉川さんと同様、ヘスターは「マグダラのマリア」の似姿であろうと思いました。「罪の女」が社会でどう裁かれ、その中でどう生き抜いたのかを描いた物語であろうと。
まず、気になった二点について書きます。
一点目は、故郷イギリスに帰ることも出来たのに、なぜヘスターは緋文字を胸に付けたままその地に留まったのか、ということです。最初はそれが腑に落ちませんでした。終盤になってやっとわかりました。〝罪を犯したこの地で贖罪の日々を生きることでこそ自分の罪は浄化される〟。ヘスターはそう考えたのですね。
「この地にとどまる」という決断は、神―我という関係性の中でこそ生まれるものでしょう。日本のような、世間―我という横の関係性の強い社会では、人は「遠くへ逃げる」しかありません。神―我の関係性の中で育つ強い自我というものを感じさせられます。私が最初腑に落ちなかったのは、それだけ自分が日本社会にどっぷりと生きていることの証しなのでしょう。
二つ目に気になったのは、娘パールの造形です。
著者はこの少女を微に入り細に入り描写します。美少女となったパールにヘスターは自らが仕立てた洋服を着せ、大層美しく装わせるのです。野外に出ればパールは自分を野の花で飾り立て、その姿はまるで妖精なのです。しかし、その振る舞いたるや、突然大声で叫び出したり、母以外の周りの世界を〝敵視〟する「悪魔の子」のように描いてもいるのです。
―うわーっ、一番嫌いな子供のタイプ! そんなことを思いつつ、このパールがどう成長していくのか、という点にも興味がありました。
さて、ヘスターと娘パール、牧師ディムズデール、幸せな出会いであったならば〝聖家族〟のように生きられたこの三人の世界に、ヘスターの(行方不明だった)夫チリングワースが突然参入して来ます。そして、二人への復讐、特に牧師への復讐心に燃え悪魔のように牧師を追い込むのです。この辺りはサスペンス小説さながらです。
この四人が不思議なリアリティをもって物語の中で生き、苦悩とつかの間の喜びと、そしてクライマックスののちに物語は終了します。
終了。ほっ。・・と思いきや、最終頁にこんな文章が挿入されるのです。
(女性たちは)心の重荷を負ったときには―― ヘスターの小屋にやってきて、わが身の不幸をなげき、どうすればよいのかを問うのだった。ヘスターはできるだけよく彼女たちをなぐさめ、その相談に乗った。
また彼女が自分の堅い信念を彼女たちに披瀝して言うには、神のみこころがこの世でも行われる天国の時代をむかえる準備がととのい、もっと明るい時代が来れば、新しい真理があらわれて、男女のすべての関係が相互の幸福というもっともたしかな土台の上に築かれることになろうというのであった。
年若いころ、へスターは自分のことを預言者として宿命づけられた女ではないかとむなしく想像したこともあったが、しかし、もうずっと以前から、神聖で神秘的な真理を伝える使命が罪によごれ、恥にうなだれ、一生の悲しみを背負った女に託されるはずがないことを知っていた。
なるほど、来たるべき啓示をもたらす天使や使徒は女性であるにちがいない。しかし、そういう女性は気高く、清く、美しく、しかもそのうえ、暗い悲しみによってではなく、天上的な喜びを媒介として賢明になり、かつ神聖な愛がわれわれをどんなに幸福にするかを、そのような目的にかなった人生の真の試練をへて示すことができる女性でなければならない!
このようにヘスター・プリンは言って、悲しげな目を緋文字に落とした。 (後略)(下線は葉葉)
え?え?なにこれ?100年後の北米から始まる女性解放思想に通じる文章じゃないの。そんな物語だっけ?
もう一度ぱらぱらと頁をめくり、小説を遡ってみました。すると、最初読んだ時は筋を追うのに精一杯で、それで見逃した細部がいろいろあったのですね。
例えばこんな箇所です。
ヘスターが皆から忌み嫌われ、町外れで娘と孤独に暮らしたが、生活に困らなかったのは、
それは、今も当時も、女性が身につける事の出来る唯一の技能――針仕事 (岩波版P117)
があったからだ、というのです。女にはそれ以外に就ける仕事が無かったという時代性が描かれます。
また、アン・ハッチンソンという処刑された実在の女性宗教家についても所々で点描されます。
更に、こんな箇所にも気付きました。
実際、女性全体について(略)暗澹たる疑念が彼女の心に浮かぶことがあった。
女性の中で最も幸せな者にとってさえ、女性としての人生は生きるに値するだろうか?
自分自身の個人的な人生に関するかぎり、彼女はとうの昔に否定的な答を出し、すでに解決ずみであった。(「13 ヘスターの別の見方」同P237)
ドキリとしますね。そして、こう続きます。
「思索癖は、男の場合と同様に、女に平静を保たせるが、女の心を悲しませることにはなる。女性の前途にたちはだかっているのは、絶望的に困難な仕事である。
まず第一歩として、社会の全組織を解体し、あらたに再建しなければならない。
それから、男性の本性そのものを、あるいは本性そのもののようになってしまった、男性が長い間につちかった習慣を変えねばならず、そうしてはじめて女性は正当で妥当と思われる地位を獲得することができるのである。
そして最後に、他のすべての困難が排除されても、女性はこういう手初めの改革から恩恵を受けることができるようになるためには、女性自身がより大きな変化をとげなければならないのである。
そしておそらく、そういう変化の過程で、そこにこそ女性の生命の真価があるところの天上的な資質は、消えてなくなってしまうことであろう。思索によって、女性はこういう問題を克服することはできない。 問題の解決は不可能であるか、あるいは唯一の解決法しかないのである。 女性の心情がたまたま前面に出てくれば、問題は消滅する。
そういうわけで、心が正常で健康なときめきを示さなくなったヘスター・プリンは、あてどもなく暗い精神の迷路をさまよい、越えがたい絶壁に行く手をはばまれては進路を変え、深い断崖をまえにしては引き返すのであった。 (同ページ)
この箇所には驚きました! 前半部には全く同意見だからです。
私も女性の解放とは、社会通念の改革、男の意識改革、それだけではだめ。最後に残る「自分(女)に内在化した女性蔑視」の克服が必要だと考えています。
この小説が書かれた1850年とは、日本の万延元年。まだ鎖国中。そういった時代にホーソンが既にこの洞察にまで達していたことに驚かされます。更に言うなら、異性である男にも関わらず。
そして同時に、ホーソンは、上記のように、
「そのような変化の過程で、そこにこそ女性の生命の真価があるところの天上的な資質は、消えてなくなってしまうことであろう。」
とも考えているのです。
この部分、『緋文字』から170年後の私達はホーソン氏に返答する必要があるでしょう。
女性解放によって女性の真価は消えてしまうのか?
そもそも、女性解放の過程で消えてなくなってしまう〝女性の天上的な資質〟って何?
よく言われる、女の優しさ?女の細やかさ?それとも母性?
優しさ、細やかさが要求されるのは今や男も同じです。子育ては母も父も共に担う時代。
母性という言葉に代って「親性」という言葉も登場しています。
しかし、ホーソン氏にはっきり返答できるほどに世の中はまだ成熟していない気がします。
アメリカ大陸にやってきた清教徒の六代目として誕生したナサニエル・ホーソン(1804年生)。
由緒ある清教徒の家柄であり、セイラムの魔女裁判で鉄拳を振るった祖先を持つホーソンには、その贖罪の意識があったと共に〝女とは何なのか?〟という深い問いかけがあったに違いありません。そして、「序章」が語るように、税関勤務時、偶然目にした古い資料をもとにヘスター・プリンという女性を創造し、小説へと昇華させたのでしょう。(古い資料云々はフィクションという説もある)
最終頁で、
「来たるべき啓示をもたらす天使や使徒は女性であるにちがいない。」
と語るヘスターは、
しかしながら、そういった神聖な使命は、
「罪によごれ、恥にうなだれ、一生の悲しみを背負った女」ではなく、「気高く、清く、美しく、(略)天上的な喜びを媒介として賢明になり、(略)人生の真の試練をへた」女性こそが担えるのだ、と考えています。
これは、ヘスターがまだ(男中心)清教徒社会の強い縛りの中にいることを物語る部分です。
ヘスターは厳しい戒律の中で苦悩し、戦い、死んでいった。
では娘パールはどんな生涯を送るのでしょう。パールはあの悪魔的義父チリングワースから思いがけず多額の遺産をもらい受け、イギリスに移住することになります。パールのその後は描かれません。
ここからは私の想像、妄想です。
娘パールは、「罪の子」というレッテルから解放されても、イギリスの男社会の中でやはりもがき苦しむことでしょう。鋭い感受性の持ち主ですから。
そして突然大声で叫んだり、神経症を発症したりもするでしょう。
性差別のくびきを打ち破るには、パール、パールの娘、更に孫娘、更にその次、と何世代もの女達を経なければならないのです。
そして日本では今も道半ば・・。
こうしてみると、『緋文字』は女性解放の黎明を感じさせる小説ですが、そう限定してしまうのも又ためらわれます。
主人公ヘスターはこうも語っているからです。
最終頁を再度引用します。
「神のみこころがこの世でも行われる天国の時代をむかえる準備がととのい、もっと明るい時代が来れば、新しい真理があらわれて、男女のすべての関係が相互の幸福というもっともたしかな土台の上に築かれることになろう」
ここにいるのは「裁きの神」ではなく「赦しの神、慈愛の神」です。
つまり、「神の慈愛のもとでの男女相互の幸福」をヘスターは言っているのです。
そう考えると、緋文字「A」とは「アガペーAgape」(=神の無償の慈愛)のAと考えることもできます。そこが単なる社会movementの女性解放運動とは違うところです。
この文の最初に私は、「ヘスターはマグダラのマリアの似姿では」と書きました。
吉川さんもマグダラのマリアについて付記されていましたが、近年、フェミニスト神学者達の聖書外伝等の研究から、マグダラのマリアは使徒ペトロに並び立つ使徒であった事が解明されてきました。教会の教父たちの解釈により、彼女の真価は隠され消されてしまったという事も。
マグダラのマリアは姦淫の現場で取り押さえられ、石殺しの刑の寸前でイエスに救われた女性ですが、のちにイエスに従って生き、重要な使徒となるのです。(※脚注A)
ホーソンはそこまでは知らなかったでしょう。
マグダラのマリアこそ「罪によごれ、恥にうなだれ、悲しみを背負い」ながら「使徒」として初代教会を支えた女性なのです。
以上、深読みに過ぎないかもしれませんが、『緋文字』はこんな視点からの物言いも可能にしてくれる、実に懐の深い小説でした。
現代でも多彩な読み解きができる『緋文字』。そこが古典と言われる所以ですね。
いつか再読した時に『緋文字』はまた違った色彩を見せてくれるに違いありません。
読むきっかけを与えて下さったお二人に深く感謝いたします。 以上
(※脚注A)「通信二号」吉川さんの論考の(注1)にあるように、「マグダラのマリアとは誰か?」についての議論は多々ありますが、私の恩師押田成人神父はヨハネ8章1~11、11章1~45、19章25に書かれた女性を全て同一のマグダラのマリアと洞察します。(『漁師の告白―ヨハネ伝』押田訳福音書、P50、50、62の註釈)
そう考えると、(後の教父たちが、マグダラのマリア(=罪の女)と使徒マリアを別人と解釈したにせよ)、イエス自身は改悛のマグダラのマリアを重要な使徒としたのです。
―この原稿は、『吉祥寺キリシタン研究会通信』第四号(2021/3)から転載しました。―
追記
最近知ったが、HP「松岡正剛の千夜千冊」も『緋文字』を取り上げている。
それによると、昔の新潮文庫版、岩波文庫版共に、あの長大な「序章」は省かれているのだそうだ。私のように辛抱の足りない読者の為だろうが、随分乱暴なことをするものだ。また、(上記レポートにも名前を出したが)、処刑された女性宗教家「アン・ハッチンソン」がヘスターのモデル、ハッチンソンを追い詰めた「牧師ジョン・コットン」が牧師ディムズデールのモデルであると松岡氏は語っている。 →松岡正剛の千夜千冊、1474夜『緋文字』