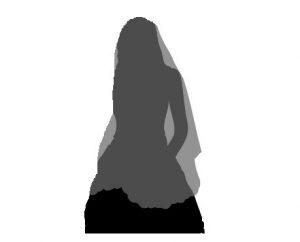『サラ・スペックス、知られざる少女。』その15

第七章 結婚
説教師カンジジウス Georgus Candidius, 1597―1647
『バタヴィア城日誌1』平凡社(東洋文庫170) P222 (下線は著者)
ドイツのファルツ出身であるが、三十年戦争の災害に悩む国を去って(一六二一)ライデンに学び、ダンカールツ Sebastiaan Danckaerts の影響を受け、一六二三年東インドに渡った。二五年モルッカ諸島の宣教師としてテルナーテの布教を命ぜられたが、長官ジャックス·ル·フェーブル Jacques le Febreと不和で翌年バタヴィアに送り還された。二七年中葉からは台湾の布教に従事、三一年末まで主として新港で勤務した。 バタヴィアに戻り、この間ジャックス·スペックスの庶子、若年のサラ·スペックスと結婚、噂のたねとなった。
1632年4月。
オランダ領バタヴィアのオランダ改革派教会の門前に一枚の紙が掲示された。ある一組の結婚の告知であった。末尾に〝この結婚に異議ある者は速やかにその旨を申し出るべし〟と書かれていた。
この告知は、早朝、両替商の妻メリッサ・カーメルの目に触れるやたちまちテレサ・ダンデバル夫人の耳に入り、それからテイヘル運河沿いの貴婦人達へ、次いでカリブ・サール大運河沿いの住宅街へと広まった。
教会門前の一枚の紙きれは、正午を告げる市庁舎の鐘が鳴る頃には、バタヴィアの上流婦人達にあまねく知れ渡ることとなった。
この噂の渦中にいて、当事者二人だけが蚊帳の外だった。
ジョルジウスは、その日の午後、牧師館を出てヘイルン通りで上級商務員の妻エセルと出会った。夫人は会釈もそこそこに慌てて立ち去った。次に遭遇した婦人からまた同じ処遇を受けて、初めて彼は自分達の婚約が街中に知れ渡ったことを悟った。
サラはその日、朝起きて顔を洗い、身支度をし、家族と朝食をとった。父スペックスは妻の体をいたわった。食卓の世話はサラが代りを務めた。継母は出産を終えて間もなかった。スペックスにとっては15年ぶりの我が子の誕生であった。男の子だった。ヤコブス Jacobus と名付けた。
スペックス家に平和な日々が訪れた。ヤックスは日に日に母の顔になってゆく妻マリアを眺め、一方で嫁ぎ行く娘サラを眺めた。
スペックスが林の中の二人を見たのはその年の初めであった。その光景は、当時、昼も夜も彼の心を波立たせた。
― よりにもよって。
ヤックスは思った。
― 口を開けば主の御言葉を語り出すような、そんな男が何故サラと。
― 憐れみか? 英雄心か?
数週間たった頃、私邸に初めてカンディディウス牧師が訪れた。
ヤックスが応接間に入ると、牧師の傍らに娘がひっそりと座っていた。
ヤックスは知らぬ風を装った。
「おぉ、これは、カンディディウス牧師様。いかなる御用でございましょう」
牧師は緊張して立ち上がった。サラはおずおずと父を見た。
「スペックス様。御多忙中、恐縮でございます」
「まあ、おかけなさい」
牧師はソファにぎこちなく座った。
「どうなさいました?」
「驚かれることと存じますが・・」
「はい・・?」
「お嬢様と・・。お嬢様とお付き合いさせて頂きたく・・そのお許しを願いに」
「お付き合い・・・ですと?」ヤックスは鼻で笑った。
「これはまた唐突な・・・」
ヤックスはサラを見やり、次いで牧師を意地悪く見た。
「唐突すぎて、飲み込めませんな・・いやはや・・・。そもそも・・」と尚も牧師に目を当て、
「カンディディウス牧師、あなた様は・・・台湾原住民との結婚を願っておられた。確かそのように記憶しておりますが・・」
牧師は、澄んだ目をヤックスに向けた。
「神がお望みならば、現地の女性と結婚しても良いと考えたのです。お嬢様と出会うずっと以前のことでございます」
「帰ってくれ給え!」
ヤックスは席を蹴って立ち、それで初回は終わった。
ヤックスは政務に没頭した。実際、タイオワン事件(浜田弥兵衛事件)は日本で硬直状態が続き、平戸オランダ商館はヤックスの采配を矢継ぎ早に求めて来たし、片や台湾のオランダ商館からは、台南近海での海賊ヤングラウの蜂起という頭の痛い報告もあった。ヤックスはこれらの難問に集中した。が、一息つけばたちまち二人の顔を思い出すのだった。
内憂外患! あぁ神はこの俺をどこまで試みられるつもりか。
思えば神は俺に絶えず難問を出した。スペイン、ポルトガル商人との戦い、幕府との駆け引き、平山常陳事件のあれこれ・・。獅子奮迅とは俺のこと。金銀銅のため幼児にぬかずき、最後は十七人を前に知性の限りを尽くし、レンガをこつこつと積み上げて掴んだ〝東インド総督〟という王冠・・・王冠を手にした途端、それが泡と消えたのだ! たかが娘ゆえに。
あの頃、バタヴィア市民は俺を〝スペックス総督〟ではなく、〝淫売の父〟と呼び、陰でほくそ笑んでいた。俺はそれを耐え忍んだ。サラが灰色のヴェールをすっぽりとかぶり人々の視界から消え、ようやく事件も風化し始めた頃に持ち上がったこの話・・。相手はカンディディウス! ばかな! これから起こる愚民どもの噂話が俺にはもう聞こえる。
― 主に拾われたマグダラのマリア!
― あのあま、今度はまたどんな手管でジョルジウスを誘惑したんだ?
またあの事件が何度も何度も掘り返される!
あぁ、あぁ、なぜよりにもよってカンディディウスなのだ。
再び牧師が訪れた時、ヤックスは、「結婚は許さない」ときっぱり言った。
蛮族への布教がどんなに危険なことかを諭したらサラは翻意するとまだ考えていた。
「いずれ君は未開の地へ行くのだろう?娘をそんな場所に手放すつもりはない。君も散々危険な目に遭ったではないか。蛮族が襲撃した時、どうやって娘を守るのだ。今しも台南では海賊が大暴れしておる」
「新港は内陸の町でした。教会脇には兵舎があり、堅固に守られておりました。そして先住民が襲撃するのは、こちらを敵と見なした時だけです。台湾におりました時、私の周囲は平和でございました」
ヤックスは牧師の仕事ぶりを長官の書簡によって熟知していた。原住民と政庁との対立の時に原住民が仲介を頼むのは、この牧師以外にいなかった。カンディディウスが平和の使いであることを誰よりも知っていた。
牧師はヤックスの疑念の一つ一つに誠実に応えたが、ヤックスは固い表情を変えることはなかった。
ある日のことだった。再び牧師が現れ、娘がその隣にまたひっそりと座った。応接間に妻マリアと召使いたちが冷茶と菓子を運んできた。マリアはヤックスの隣に腰を下ろし、夫と牧師との会話に耳を傾けながら、落ち着かせる様に夫の手を握った。その手のぬくもりが、外堀が埋まったことを示していた。
ヤックスは、もはや語気を荒げはしなかった。
「せめて」とため息をついた。
「せめて・・・このままバタヴィアの教会にとどまってはくれぬか」
牧師は静かに首を振った。
「父上様。新天地への布教を生涯の使命と考えています。どうか、お許し下さい」
「・・・。ならば、その時は君が単身で向かってくれるか?」
今度はサラが首を振った。
ヤックスは尚も、「ならば」「ならば」、と応戦しながら、己の言葉が二人の上を上滑りして消えていくのを感じた。俺が何万言費やそうがこの二人には届かぬ。
そして、普段そこからは何も聞こえない、しんとした場所から低い声がした。―もう、いいんだよー
その声は、体のどこか深い所に落ちていった。熟した木の実の落ちる音がした。
もう、俺の力の及ぶ所ではないのだな。そうさ、あの日、林の中で二人を見た時、もう俺は気付いていたではないか。
教会の門前に紙が掲示されたその日。
家族との朝食を終えたサラは、二階の自室で婚約者の手記 ―台湾報告― を読んだ。台湾という日本に近い国。まだ見ぬ風景。シラヤ人・・。サラには夢のような別世界に思えた。― この時サラは、のちに台湾で二人を待ち受ける避けがたい事件について知る由も無い― そして午後には針仕事をした。花嫁衣裳を飾る和刺繍である。糸通しから始まって、玉結び、玉どめ、平縫い、返し縫いとトシが辛抱強く教えた。裁縫は、城を出て、夫と二人で生きる為にも必要だった。和刺繍独特のふっくらとした花びらが作れた時、サラとトシは顔を見合わせて喜んだ。純白の絹に桜の花びらが一つ一つ増えていった。針仕事にサラは時を忘れた。
いつもの時間にトシが現れた。
「お嬢様、ごきげんはいかが」
そう言った後、少しの間を置いてトシがぽつりと、
「すでに街中が知っております」と言った。
サラは、「そう」と言って裁縫を続けた。
桜色の刺繍糸も銀糸も調達済みである。サラはしばらくは総督邸から外ないことにした。
結婚への異議申し立ては無かった。その翌日、規則に従って再び告知が出された。異議申し立ては無かった。そして三度目の告知が出され、異議申し立ては無く、教会は二人の結婚を受諾した。
挙式は5月20日と決まった。
挙式について誰よりも心を砕いたのはトシだった。これが私の最後の務め・・トシはそう決めていた。バタヴィア一のオランダ改革派教会はあの市庁舎近くにあり、怪死した総督クーンが葬られた教会でもあったので、トシは頑として反対した。式場としてトシはバタヴィア城内聖堂を主張し、周りに有無を言わせなかった。
真昼の灼熱を避けるために式は朝七時から執り行われることとなった。
早朝、バタヴィア城の正門が開くと、待ち構えたように二頭立て、三頭立ての馬車が賓客を乗せて次々に入城して来た。招待から外された者達も何とかして城内に入ろうとし、門番に ―ところで、かつての門番トマスは、事件後、バタヴィア外門から追い出された為、おそらくマタラム軍に八つ裂きにされたか虎に喰われた―、この新門番に袖の下を握らせた。メリッサ夫人、ダンデバル夫人もその中にいた。次第に城内が混乱し始めると、兵隊長は警護のために急遽、衛兵三百人を追加した。
時間になった。聖堂に入りきれなかった群衆が教会の外廊から中庭へとはじき出された。かろうじて聖堂に席を確保できた人々は首を伸ばして花嫁の登場を今か今かと待った。
鐘楼の鐘が三度鳴り響いた。パイプオルガンの音と共に白い正装の子供たちが二列になって花束を手に歩いてきた。
そこに、総督と花嫁が姿を現した。
十五歳の花嫁である。華奢な体を包む白いドレスがまず目を引いた。裾には銀糸で流水が描かれ、そこに桜の典雅な花模様が散りばめられ、衣装が動くたびに花びらがはらはらと舞った。顔を覆う白いヴェールはまっすぐに腰まで流れていた。花嫁は背を伸ばし、顔を上げ、父と共に歩を進めた。
かつて、公開処刑を見物していた者達は、半裸で、素足で、広場をたった一人とぼとぼと歩いていた光景を脳裏に蘇らせた。その少女が三年後、華燭の典の、その中央を、純白の衣装で一歩一歩たしかな足取りで歩いているのである。この姿を予想した者など誰一人としていなかった。
花婿が待つ場所まで進むと、父は娘の手を花婿に渡した。花嫁は花婿を見上げ、花婿は花嫁を見て二人小さくうなずき、そして祭壇に向かって歩を合わせ静かに進んだ。祭壇脇にはヘルマン牧師が立っていた。
花嫁はヴェール越しに、参列席で涙を流すトシの姿を認めた。家庭教師フリードリヒを探そうとして、もういないことを思い出した。
親族席には継母マリアと赤ん坊のヤコブスがいた。その隣には上級商館員アレント・ヘルデネイス Arent Stevensz Gardenijs と、アレントと結婚したばかりのマリアの妹ゲルトルード Geertruid Odilia Buys がいた。ゲルトルードは、オランダからバタヴィアに嫁いで来たのだった。
貴賓席には華人代表の蘇鳴崗とその夫人が、更に日本人代表として楠市右衛門とその夫人がいた。
永遠の愛が誓われる時のことだった。花嫁のヴェールが取り除けられると、サラ・スペックスの素顔がさらされた。ほっそりとした卵型に髪の毛は淡い栗色である。長い髪をきっちりと高く上げてまとめ、美しい顔の輪郭を際立たせていた。瞳はくっきりとしながら優しい。唇には 薄紅に紅が差してあった。
メリッサ・カーメルは口をぽかんと開けた。令嬢を淫売と呼び続けたことは忘れ去り、「まぁ、まるで真珠」とつぶやいた。日本から追放されたキリシタンの一人、楠市右衛門の妻は聖母になぞらえて、「なんと、お前様。百合の花のごたるなぁ」と夫にささやいた。
背が違い過ぎるので花婿は身をかがめて花嫁に近づいた。花嫁は優雅に、堂々と花婿の口づけを受けた。その振る舞いは列席者にある種の印象を残した。列席者の誰もが、このような美しく気高い娘がこの町にいたことに驚いたのだった。
二人の退場とともに、鐘楼の鐘が連打された。パイプオルガンの音色と聖歌隊の調べが聖堂に満ちた。
聖堂の扉が開くのを民衆は外で待ち構えていた。二人が現れると、兵隊長が「カンディディウス牧師様、おめでとうございます!」「サラお嬢様、おめでとうございます!」と高らかに叫んだ。すると弾ける様な歓声が二人を包んだ。民衆は掌にナツメグの白い花びらを持ち、二人が通るたびにその頭上に撒いた。無数の花びらが太陽の光を受けてキラキラと青空に舞い上がった。
扉から開け放たれた祝福の歌声は、教会の鐘の音とともに、聖堂から中庭へあふれ出て、バタヴィアの数々の悲しい歴史をひととき慰めるかのようにバタヴィア城を満たし、風の様に自由気ままに渦を描きながら、ジャワの紺碧の空へと消えていった。