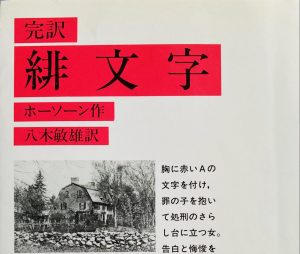『サラ・スペックス、知られざる少女。』その14
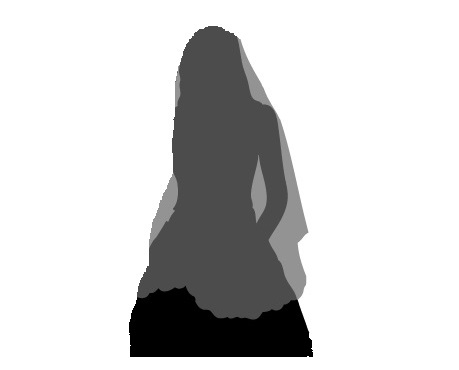
- 第六章 牧師カンディディウス
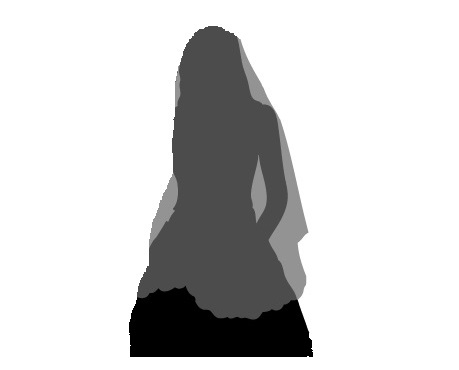
牧師カンディディウスは寛永四年(一六二七年)渡台後、新港社に居住して原住民語を学んだうえ布教に着手し、同五年には前に掲げたごとき失望の声を発するに至ったが ※ 、翌六年(一六二九年)渡台した牧師ユニウス Robertus Junius と心を合わせて教化に努力した結果、同八年(一六三一年)初めには、新港社の受洗者が五十人にのぼった。
同十三年の帰順式後に学校を開き、少年七十人を集めてローマ字を教え、キリスト教要理を授けたところ、大目降、目加溜湾、蕭壠、蔴豆等付近の諸社においても、これに倣って学校を設け会堂を建つるに至り (後略)
『バタヴィア城日誌2』-序説-(東洋文庫205、昭和47年、平凡社)
※1628年、台南でおきたタイオワン事件(浜田弥兵衛事件)を端緒として、台湾でのオランダ人への信頼が失墜し、多数のオランダ兵が台湾人に殺されるなど、カンディディウスの身も危うくなった事を指す。尚、文中の「社」とは村落、地域の意味。
サラ・ピーテル事件から2年が過ぎた1631年12月のある日。
ジョルジウス・カンディディウス牧師は宣教師としてめざましい業績を上げながらも台湾政庁から解任され、一旦バタヴィアに戻った。
5年ぶりの帰還だった。
「ジョルジウス! 」
旧知のヘルマン牧師がカンディディウスのもとに真っ先に顔を出した。
「数々の危機をよく御無事で!」
「ヘルマン!」
二人は固く抱き合った。
「布教も軌道に乗り始めて・・。なによりだが・・」
「ああ」
「なのに解任とは・・」
「ヘルマン、またか、と思ってるんだろう。前回はル・フェーブル、今回はプットマンス・・」
「思わないさ。誰が何と言おうと、君は評価に値する」
ヘルマンはカンディディウスの肩をポンポンと叩いた。
カンディディウスの布教方針は革新的だった。それまでの牧師達が現地人にオランダ語を教えるのに躍起だったのに対し、彼は自ら現地語を学び、現地語で聖書を教えた。台湾に赴任した際も、敬意をもって台湾人と接した。現地人と絆を結べた牧師は彼が初めてと言っていい。
更に踏み込んで、彼は自分と現地の女性との婚姻が宣教のために良いと考えた。
ここに派遣される聖職者はその妻をこの地に伴うべきであります。さすればサタンの罠に陥らずに済むことでしょう。
彼は彼の家族によって、聴衆に対して、正直さ、高潔さ、正しさの生ける鑑となり、人々はそれを手本に自分自身を振り返ることが出来るのです。
牧師が独身の場合、現地の女性を娶ることは更に良いことと考えます。
(1628年12月27日 台湾長官 ピ‐テル・ノイツの質問に対するカンディディウス牧師の返答)
『FORMOSA UNDER THE DUTCH』註釈(14)REV.WM CAMPBELL P92、PARTⅡ ― Memorandum from Candidius on theChristianising of Formosa
牧師の意向は台湾政庁のみならず、バタヴィア政庁でも物議を呼んだ。
総督クーンからすれば、〝一等人種と、四等にも劣る台湾原住民との結婚など論外〟であった。
台湾長官ハンス・プットマンス Hans Putmans は総督に報告を繰り返した。
〝1630年2月24日〟の日付のある総督宛の手紙――クーンの怪死は29年だが、台湾に訃報が届くのは30年6月のため――に長官はこうも記している。
また私たちは彼(=カンディディウス)が原住民の一人と結婚するに違いないと思っています。
(同資料P100 letter5)
クーンの業務を引き継いだ新総督ヤックス・スペックスは次の様に返信した。
最も賢明にして公平な紳士である貴殿(長官)から、1630年10月8日、12月28日、そして1631年2月20日、22日、3月6日、17日と手紙が届きました。それらを読みまして私は返事を書いております。
まず、新港の住民にキリスト教徒が増加し、発展を見せているというその知らせを私は大いに喜んでおります。
カンディディウス牧師のたゆみない宣教熱は、まったくもって賞賛に値します。
しかしながら、物事が全てそうであるように、何事にもある程度の節度と自重とが示されるべきです。
貴殿はこの布教を会社に負担をかけない方法で実施、促進すべきであります。牧師が要請する台湾の貧しい人々への金銭的援助は新港人自らが行うべきです。
すでに新民族たちを支援している私達オランダ人が負担を強いられるべきではありません。
ここバタヴィアでも他でも、新港よりも多くの援助を必要とする善良なるオランダ人信徒は山ほどいるのです。
そして会社の貿易は損失も多く、新港の原住民に金品を援助することなどほとんど不可能であります。加うるに、毎年台湾の聖職者たちに与える年四千ギルダーの支払いのために我々の資金は大いに枯渇しております。
また、こうも考えるべきです。
譬えて言うならば、原住民が田んぼからの収穫を心待ちにしているように、会社は、毎年、不安を覚えながら何年も前の出資金からの利子の受け取りを心待ちにしている困窮したオランダの未亡人や孤児のことをいの一番に考えなければならないと。
カンディディウス牧師の嘆願は我が社の一般規則に相反するものであり、上述の通り、会社の財政状態によっても残念ながら同意することはできません。(中略)
また彼の結婚についてですが、我々はカンディディウス牧師の〝地域社会の利益のため〟という視座に立った婚姻は讃えられるべきであるものの、そのような婚姻から生じる公的及び私的な利益、並びに不利益とを考慮すれば、如何なものでしょう。
公的な利益と彼本来の自然性とを考え合わせた時に、彼は現地女性との結婚を拙速に行うべきではないと考えております。
(1631年7月31日 総督スペックスから台湾長官プットマンスへ)
(同資料 P103 letter11)(下線は筆者)
牧師のあずかり知らぬ所で、彼の幾つかの嘆願や現地女性との結婚問題は頻繁に議論されていた。
そしてこの時、ヤックス・スペックスはこの牧師が将来、わが娘婿になる事など想像もしなかっただろう。
ヘルマンはあけすけに言った。
「宣教費増額の訴え、牧師は政治的仕事を一切しない宣言・・。実を言えば〝カンディディウス案件〟の担当者はこの私だ」
「カンディディウス案件・・・」
彼は溜息をついた。そしてふとドアの方に頭を上げた。
ドアから漏れる女達の囀り声がさっきから気になっていたのだ。
「誰かいるのか?」
「そう。君をお待ちかねなんだよ。聖書の勉強を希望しておられるのさ」
「構わないが・・」
ヘルマンがドアを開けると、花の様な装いの令嬢達が一人一人優雅に挨拶しながら入室してきた。母親連れもいる。それぞれ数人の召使を従えている。女性たちの中には以前会ったことのあるシルフィア・デーネンがいた。バタヴィア政庁の評議員デーネン氏の令嬢であり、オランダ生まれである。またルイサ・ヴィンケルもいた。久々に出会う白い肌の女性達だった。
「皆様、貴殿から福音を学びたいのだ」
「私などでよろしいのですか?」
「ジョルジウス様が良いのです!」
一人の令嬢が黄色い声を上げた。
牧師は苦笑した。
―ヘルマンは相変わらずこの中から聖女を探せと言うのか。
東南アジア派遣を志願する牧師は、せいぜい本国から放逐された問題児か、牧師の口にあぶれた落ちこぼれが多かったが、この改革派教会のホープは、宣教熱にかられて海を渡ったのである。彼がVOCの方針に従わない〝孤高の牧師〟であることは狭いバタヴィア社会に既に広まっていた。聖人をいや英雄を一目でも、と女性たちが教会に詰めかけたのだった。
日曜礼拝でのカンディディウスの説教にも特徴があった。凡庸な牧師が笑みを浮かべながら空疎な美談を朗々と話すのに対し、カンディディウスはむしろ寡黙と言ってよく、訥々と、時に言い淀み、沈黙し、また訥々と語りかけるといったもので、それがまた彼の評判を上げた。
クリスマスが近づいていた。熱帯のクリスマスである。
カンディディウスは凍えるようなオランダの聖夜を思い出し、台湾の聖夜を思い出した。
台湾は摂氏10度を下る事などなかったが、それでもいつもより涼しい時期のクリスマスであった。
不図窓から外を眺めると、灼熱の地で老若男女のバタヴィア市民が教会の樹木に綿を飾り、リボンを下げ、飾りつけにいそしんでいた。故郷を思い出している者、オランダに行った事もない者、半裸の使用人たちもキリストの誕生を祝う準備をしているのだった。
12月25日、早朝。
まだ人もまばらなクリスマスの早朝礼拝に、風変りな五人連れが現れた。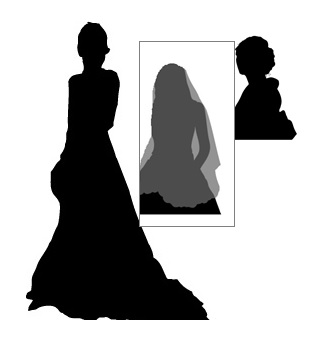
若き貴婦人と、その隣には十代の少女、二人の後ろには三人の付き人がいた。
異様なのは少女であった。全身が灰色である。腰まで届く灰色のヴェールで顔を隠し、灰色のドレスに身を包み、亡霊さながら音も無く入堂してきた。美しい貴婦人と、亡霊のような少女。物言わぬ三人の付き人。まわりとは異質な人々であった。そして、会衆が五人を避けるように着席するのも奇妙であった。
早朝礼拝には、クリスマスのお祭り騒ぎを嫌う人々が集う。
カンディディウスが大切にする人々である。
「こちらに参りまして、よく皆様からこんな質問を頂きます」
彼は語り出した。訥々と、時に沈黙しながら。
「蛮族が怖くはないですか? 主の御言葉を蛮族が理解できるのですか?と。・・・福音とは〝良き便り〟の意味。良き便りは全ての人々への便りなのです。私の務めはそれを届けることです。国も民族も越えなければなりません。・・・ある村で・・村の更に奥地です。一人の青年が、ある聖句を聞くと、急に泣き出しました。・・・その聖句とはマテオ福音書の山上の垂訓です。イエスが丘の上で弟子達に語った言葉です。
砕かれた人は幸いである。天国は彼らのものだから。
泣く人は幸いである。彼らは慰められるから。
柔和な人は幸いである。彼らは地を受け継ぐから。
飢え渇く人は幸いである。彼らは満たされるから。
憐れみある人は幸いである。彼らは憐れみを受けるから。
心の清い人は幸いである。彼らは神を見るから。
平和を生む人は幸いである。彼らは神の子と呼ばれるから。
義の為に迫害される人は幸いである。天国は彼らのものだから。
青年は言いました。〝砕かれた人〟〝餓え渇く人〟とはこの私、と。・・・その村はやはり今日、主の生誕を祝っております。青年は教会の柱となり、主の御言葉を届ける人となりました。・・・皆様が〝野蛮〟〝未開〟とおっしゃる村々でこそ、主の御言葉は息づいております。・・・主は貧しい人々とともにあった。・・・それを思い起こしましょう。今日、主が幼な子として地上に誕生したことを味わいましょう。・・・アーメン」
礼拝を終えると、ヘルマンが近づいて来た。
「ジョルジウス、あの五人連れをご覧になったか?」
「 ああ、あの風変りな? ・・・ええ、拝見しましたが・・」
「真ん中の少女・・あれは総督スペックス殿のご令嬢だよ」
「スペックス殿の?」
カンディディウスは遠い記憶を手繰り寄せた。
総督がまだ事務総長だった頃、城の大広間で会話を交わしたことがある。傍らに小さな少女がいた。それが今朝のあの灰色の人物であろうか。
「そうでしたか・・ほんの小さな頃にお目にかかりました。快活で愛らしく・・あぁ、随分と様子が変わられ・・全く気付きませんでした」
「ごもっとも」
ヘルマンはニヤリと笑い、「ここだけの話」と声をひそめた。
「淫売と言われてるのだよ」
「淫売?」
「まあ、大変な事件を起こしてね」
ヘルマン牧師の口からカンディディウスはサラ・ピーテル事件の詳細を聞いた。
そのような事件は聞いた事があったかもしれない。台湾にもバタヴィアのスキャンダルはよく輸入されて来たから。
しかし当時、カンディディウスには同時期の「バタヴィア号事件」が強く印象づけられていた。(事件の詳細は註釈(13)として既述)
当時、オランダはカンディディウスの様に宗教戦争から逃れた新教徒、迫害から逃れたユダヤ教徒も移住してきた。プロテスタント改革派が中心ではあったが、中にはカトリック教徒も、清教徒もいれば、異端さえも棲息する、いわば宗教の坩堝であった。
殺人鬼イエロニムスは過激な 霊的 自由派 を信奉したが、その根本思想は、〝神は全知全能であり悪を犯さない。神に帰依する者の行為は全て――人の目には悪と映ろうとも――神が嘉されたものである。よって、何をしても罪とならない〟というものだった。彼は霊的自由派による「千年王国」を夢見た。その結果、幼児を含む124名の殺害という凄惨な事件を生み出した。
カンディディウスは、信仰と狂気との境目の危うさを思ったものである。
「総督クーンの怒りはすさまじく・・少年少女の処刑を誰も止められなかったんだよ」
「あの令嬢が・・それは・・気の毒に」
「土壇場でサラは命だけは救われたのだが・・」
父スペックスは、新総督に選ばれるや否や、令嬢を鞭打ち刑にした人物たち・・裁判官や判決に調印した評議員達を激しく問い詰めたのだという。
「スペックス殿の怒りもまた並々ならぬものがあってね。恒例の晩餐会―政庁や教会の要人が集う―あの晩餐会を彼は拒否したのさ。〝鞭打ちへの同意者が出席するならば、私はご遠慮致しましょう。そして、私が出席する時にはその方々はどうかご遠慮頂きたい! 〟と言って。あの晩餐会の重要性を御存知だね? つまり「寛容」を旨とする会食で、主義主張や立場の違いを越えて一堂に会するという進歩的なものさ。拒否された幹部たちはオランダ本社に訴え出たのだ。そのため本社にもサラ・ピーテル事件が明るみになってしまった。現在もなお彼は「暫定総督」のまま。日本との貿易で大成功を収め、今、また、タイオワン事件なんぞ起きると、〝スペックス様のお出まし〟と担ぎ出される。しかし、暫定総督なのだよ。身持ちの悪い娘のせいで。そして、バタヴィア社交界では今も尚、サラ・ピーテル事件が噂にのぼるのさ。尾ひれ羽ひれを付けてね。・・・そして令嬢は〝淫売〟呼ばわりさ」
あの、私の腕に無邪気に抱かれた少女が、五年後の今、全身を喪服で包み、このバタヴィアで息を殺して生活している・・・。
「憐れなことだ」
カンディディウスがつぶやくと、ヘルマンはふふんと冷笑した。
「あの美貌の継母と、亡霊のような令嬢。太陽と月。・・そして、太陽に隠れたあの月の、妖しい美しさには私でさえもゾッとする」
「ヘルマン! 口を慎め」
「あぁ・・これは失敬」
ヘルマンは親に叱られた子供のように首をすくめた。
「しかし変だな。令嬢はポルトガル教会に通っていたはずだが・・」
カンディディウスはあの頃、少女が下男らの担ぐ輿に乗って城門を出、町外れのポルトガル教会に通っていたのを思い出した。
「ああ。助命の条件が〝カトリックからの改宗〟でね、それで令嬢は城内のオランダ教会に通うようになったのだよ。この教会にも時々はご家族でいらっしゃる。会衆は騒然とする。美貌の総督夫人、そしてバタヴィアの汚辱。盗み見ぬ者はいない。そして令嬢は常に亡霊だ」
「なるほど」
年が明けたある日。
カンディディウスはバタヴィア城での日曜礼拝を頼まれた。城内の聖堂である。
総督夫人と令嬢たちは早朝礼拝に訪れた。
礼拝後、付き人の日本人に、「ご都合よろしい時に奥様とお嬢様とを隣室にお招きしたい」と伝えた。
五人は翌週の礼拝後、牧師のもとにやって来た。
マリア・オディリア。美しい女性だった。総督夫人の身分にしてベージュのドレスに真珠の首飾りだけの質素な装いだった。
夫人は微笑みを浮かべ、「わたくし、ハーグ出身です」と言った。
「私はライデンに住んでいました」
「存じています。ライデン大学を主席で御卒業とか。皆様がお噂していますわ」
「主席で卒業? 今ではVOCの落第生ですよ。ははは。奥様はハーグのご出身・・そうですか・・街も海も本当に美しい」
「ええ」
「私の出身はファルツです。あの戦争の時に家族で故郷を去ったのです」
「まだ続いておりますわ」
「ええ。今や宗教戦争とも違う複雑怪奇な・・・」
二人の会話の外側で、令嬢は床の一点を見つめ、ひっそりと座っていた。
夫人と会話しつつ、カンディディウスは令嬢をそっと眺めた。
――本当にすっかり変わってしまったなぁ。
彼は語りかけてみた。
「お嬢様」
「・・・」
令嬢は床を見つめたまま顔を上げない。
「覚えておられますか? 以前お目にかかりましたが・・。もう五年も前です。お嬢様がまだお小さい頃に」
うつむいたまま無言である。
「城の大広間で歓迎会があって、そこでお会いしました。あなたは〝マンゴーが食べたい〟とおっしゃり、二人でテーブルからテーブルへと探して回りました」
令嬢は、この時はじめて床から視線を上げた。牧師を見ることなく、ただ顔を上げただけだったが。
「そのあと、お城で時折お見かけすることもございました。お嬢様は私に気が付くと、手を振って下さり・・。はは、もう覚えてはいらっしゃらないでしょう」
「・・・」。無言だが何かを思い出そうとする風でもあった。
「それから私は 台湾 に参りまして、今までかの地で布教しておりました」
しばしの沈黙があった。
令嬢の口が動いた。
声帯が貼り付いてしまったのか、令嬢はやっと聞き取れるかすかな声を発したのである。
「フォル・・モサ・・」
そして、令嬢は小首をかしげるようにして、心持ち、顔を牧師に向けた。
カンディディウスは令嬢と目が合ったように感じた。
ヴェール越しの、令嬢の顔に初めて表情が現れた。そこには妖気など微塵もなかった。
ただ臆病に、自分が生きてあることを恥じるように目を伏せ、目を上げればその瞳には悲しみと諦めと、それしか残っていないかのようだった。その瞳にわずかに光が宿った。
「・・ジパングに・・ちかい・・フォルモサで・・しょうか」
「そうです。近いですよ」
サラ・スペックスは不意に思い出した。
家庭教師のフリードリヒが〝泳いで行けますよ。クジラに喰われなければね〟と笑った日のことを。
〝あなたなんか泳げるものですか〟と恋人と笑い合った日のことを。
幸福な場面場面がきれぎれに浮かび、それらが消えると、苦肝の苦渋が胸にじんわりと広がった。何回目の苦渋だろう。あの頃は体の傷がギリギリと痛み、毎日、毎時、毎分、毎秒、痛みに襲われた。体の傷がようやく癒えると今度は胸の痛みに苦しんだ。私は人の一生分、いや二生分の涙を流した。もう体中の水分のありったけを流した。そしてこのごろ、苦渋は、胸を締め付けず、淡い海の色のように胸の中を通り過ぎていく。ほら、今も、もう前を向きなさいと。牧師さまの静かな目は、もう前を向きなさいと言っている。私の涙は声もなく、ただ静かにこぼれるだけだ。
カンディディウスは、令嬢の頬に一筋の涙が流れるのを見た。
夫人もそれに気づき、令嬢にハンカチを手渡した。
令嬢はヴェールの中で涙を拭いた。周りの者達は息をひそめた。
牧師も同じように息をひそめ、令嬢を包む静寂の中に共にいることを感じた。
令嬢は再び顔を上げると小さく言った。
「ぼくし・・さま・・」
「はい」
「いつか・・フォルモサのお話が・・ききたい・・」
「かしこまりました」
継母と付き人は、サラが処刑の日以来、身内以外の他人と初めて口をきいたことに内心驚いていた。
控えの日本人がつぶやくように言った。「お嬢様は日本でお生まれになりましたから、台湾は憧れの地なのです」
「牧師様」。継母が深々と頭を下げた。「私からもお願いしますわ 」
継母と共に令嬢は静かに立ち上がった。そしてドレスを持ち上げ、挨拶をし、再び無表情になるとドアの外に出て行った。こうして五人は弔い客のように帰っていったのである。
次の週、五人は再び礼拝に来て、牧師のもとに立ち寄り、一言、二言、言葉を交わして帰っていった。
その次に来た時だった。
「ぼくし・・さま・・」。令嬢は遠慮がちに言った。
「いつか、バタヴィアを・・はなれる・・のですか?」
牧師には意外だった。
「誰が言っていましたか?」
「みなさまが・・おうわさを・・」
ヴェールの奥の令嬢の瞳に寂しさが浮かんでいた。
牧師は、返事に困った。台湾への再任が、よりにもよって上層部から打診され始めていたのである。
―台湾には汝の力が必要なれば早急に帰台されよ。
牧師は態度を留保していた。台湾長官が変わらぬ限り二の舞を演じるのは明らかだった。
「いえ、何も決まってはいません」
すると令嬢は、はにかむ様な表情をした。
牧師の心に小さなさざ波が立った。そのさざ波は牧師が経験したことのないものだったが、心に流れるままにした。
「フォルモサのお話を致しましょう」
令嬢はこくりと頷いた。
牧師は語り出した。拠点とした台湾南部の風俗、風習、驚いたこと、嬉しかったこと、知り合った人々の話、危険だった時のこと、スペックス総督に数々の支援を受けたこと・・。
令嬢は、牧師の話に耳を傾けた。姿勢をほとんど変えず、時に、小首をかしげ、それは笑顔を示していて、まるで野に咲く白い花が風に揺れる風情であった。令嬢が微笑むとそれに続いて周りの者達も微笑んだ。
カンディディウスは思った。まるで四人の修道女が羽の折れた小天使を見守っているようではないかと。
―あの子は・・。
仕事が一息ついた時など、ジョルジウスにふとある思いがよぎるようになった。
―今頃、何を食べてる?
―今頃、何をしてる?
―今度、いつ会える?
そして、今まで思ってもいないことを思うようになった。
―このままバタヴィアにいられたらなぁ・・・。
初恋。
牧師は頭を振って打ち消した。私はすでに三十五。令嬢はほんの十代ではないか。
そして忘れようとして忘れ、またいつの間にか、思いがそこに舞い戻るのだった。
―今頃、何を食べてる?
―今頃、何をしてる?
―今度、いつ会える?
―このままバタヴィアにいられたらなぁ・・・。
ある日の夕方のことである。
総督ヤックス・スペックスは従者と共に、市街の外れ、カイマンス運河の東南に伸びる林道を歩いていた。
市街地の視察であった。
あたりは薄暗く、けれども夕陽が林の中に差し込み、仄かに明るさがあった。
通りの向こう側に落ち葉を踏みしだきながら、長身の男と、若い女が歩いているのが見えた。
スペックスは、咄嗟に物陰に隠れた。
娘サラだった。顔を長いヴェールで覆っているのが遠目にもわかった。
そして、男女の姿を―ほう―と、意外な気持ちで眺めた。
女はうつむき加減で、男は背筋を伸ばして歩いており、時折男が話しかけると、女はそれに返事をする様子であった。
女の両手は男の左腕にあり、男はその腕を女に預けたままで右手には鞄を持ち、歩きにくいだろうに、そうやって寄り添うように、夕映えの林道を二人でゆっくりと歩いていたのである。
「その15」へつづく
(掲載は今月(7月)の予定)